取得時効の対象となる権利
取得時効は、権利者としての事実状態を一定期間継続した者に対して権利の取得を認める制度である*。
* 原始取得であって、原則として負担(地役権や抵当権など)のない完全な権利を取得する(289条・397条)。
取得時効の対象となる権利は主に所有権であるが(162条)、所有権以外の財産権についても時効による取得が認められている(163条)。
もっとも、すべての財産権が対象となるわけではなく、取得時効の対象となる権利は占有ないし継続的な行使が可能である性質のもの――地上権、永小作権、地役権*、不動産賃借権⁑などにかぎられる。
* 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものにかぎり、時効取得することができる(283条)。
⁑ 判例は、土地賃借権について、「土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているとき」に、その時効取得を認めている(最判昭43.10.8)。
所有権の取得時効の要件
所有権の取得時効(162条)の要件は、次のとおり。(以下、所有権以外の財産権の取得時効の要件については割愛する。)
- 他人の物の占有であること
- 所有の意思をもって占有すること
- 平穏かつ公然の占有であること
- 一定期間(20年または10年)占有が継続すること
- 占有の開始時に善意かつ無過失であること(10年の取得時効の場合)
民法186条1項は、「占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有するものと推定する」と規定している。
この規定は、およそ占有の事実があるときは自主・善意・平穏・公然の占有であることが推定され、したがって、占有が他主、悪意、強暴または隠匿であることを主張する者がその証明責任を負うことを意味する。
このように、ある法律効果の要件事実とされていながら法律上その事実の存在が推定されており、その事実の不存在を主張する側がその証明責任を負うような場合を暫定真実という。
① 「他人の物」の占有
民法162条は、取得時効の対象を「他人の物」と規定している。
しかし、時効制度の趣旨(永続した事実状態の尊重、証明困難の救済)や取得時効の機能する場面*を考えると、自己の物の時効取得をも認めるべきである(通説)。判例も、自己の物についての取得時効の援用を認めている(最判昭42.7.21)。
* 不動産の二重譲受人間の優劣問題(「取得時効と登記」の問題)や境界紛争など。
一筆の土地の一部のような物の一部についても、取得時効が成立する(大連判大13.10.7)。
② 所有の意思のある占有
所有権の取得時効は、「所有の意思」をもってする占有(自主占有)の場合にだけ成立する*。
* 所有の意思がない占有(他主占有)だと、地上権や賃借権などの取得時効は成立し得るが、所有権の取得時効は成立しない。
所有の意思の有無は、占有者の内心の意思ではなく、占有取得の原因(権原)または占有に関する事情によって外形的客観的に定められる(最判昭45.6.18)。
たとえば、権原が売買契約や盗取であれば所有の意思が認められるが、賃貸借契約であれば所有の意思は認められない。
占有者の所有の意思は推定される(186条1項)。したがって、占有者の占有に所有の意思がないことを主張する者がその証明責任を負う*。
* 所有の意思の推定をくつがえすためには、①占有者の占有が他主占有権原によるものであること、または、②他主占有を基礎づける事情(他主占有事情)の存在を証明しなければならない(最判昭58.3.24)。
所有権の取得時効が成立するためには自主占有でなければならず、他主占有のままではいつまで経っても所有権の時効取得はできない。
そこで、民法185条は、占有の性質を他主占有から自主占有に変更するための二つの方法を定めている。
一つは、占有者が自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示する方法であり(同条前段)、もう一つは、新たな権原(新権原)により自主占有を始める方法である(同条後段)。
たとえば、賃借人が賃貸人に対して賃料の支払いを拒否するのが前者であり、売買契約によって賃借物の権利を譲り受けるのが後者である。
後者の方法に関して、相続が新権原になるか*が問題とされている⁑。
* 他人の物を管理(他主占有)していた者が死亡してその相続人がその占有を相続により承継した場合、相続を新たな権原とする自主占有への性質変更を認めることができるかどうかという問題である。
⁑ 判例は、相続人が、被相続人の占有を相続により承継しただけでなく、①新たに当該目的物を事実上支配することによって占有を開始した場合で、②その占有が所有の意思にもとづくものであるときは、相続人は独自の占有にもとづく取得時効の成立を主張することができるとする(最判昭46.11.30)。そして、②の要件について、相続人自らが、「その事実的支配が外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づくものと解される事情」を証明しなければならないとする(最判平8.11.12)。つまり、所有の意思の推定は働かない。
③ 平穏かつ公然の占有
取得時効が成立するためには、時効期間中、「平穏に、かつ、公然と」占有を継続することが必要である。社会秩序をかく乱するような占有は、法的保護に適さないからである。
「平穏」とは占有が暴行や強迫によるものでないことであり、「公然」とは隠匿しないことである。いずれも推定される(186条1項)。
④ 一定期間の占有の継続
取得時効が成立するためには、占有状態が一定期間継続することが要件となる。
占有継続の期間(取得時効期間)は、①通常の場合は20年(162条1項)、②占有の開始の時に善意無過失である場合は10年である(同条2項)。
占有は、途切れずに継続する必要がある*。取得時効が完成する前に、①占有者が任意にその占有を中止したり、または、②他人にその占有を奪われたりしたとき、取得時効は中断する(164条)⁑。
* 起算点とその20年または10年以後の時点における占有の事実を証明すれば、占有はその間継続したものと推定される(186条2項参照)。
⁑ 他人の侵奪行為によって占有を喪失した場合であっても、占有回収の訴えによって占有を回復したときには、占有は継続していたものとみなされる(203条ただし書)。
なお、取得時効の起算点は占有を開始した時点に固定されていて、当事者が任意に起算点を選択して時効完成の時期を遅らせることはできない(最判昭35.7.27)。
⑤ 占有開始時における善意無過失
10年の取得時効(短期取得時効)が適用されるためには、占有者が占有開始の時点で善意・無過失であることを要する(162条2項)。
善意とは、占有者が占有物について自己に所有権がないことを知らないこと、つまり、自己に所有権があると信じることであり、無過失とは自己に所有権があると信じることについて過失がないことである。
民法186条1項によって占有者が善意であることは推定されるが、無過失であることは推定されない(大判大8.10.13)。したがって、10年の取得時効を主張する者は、自らが無過失であることを証明しなければならない。
なお、占有者は占有開始の時に善意・無過失であればよく、占有継続の途中で悪意に変わっても10年の取得時効の成立を妨げない(大判明44.4.7)。このことは、占有主体に変更があって、占有の承継人が自己の占有期間に承継した占有期間を合算して主張する場合にも当てはまる。
占有は、売買による譲渡や相続などによって承継することができる。そして、占有の承継人は、自己の占有のみを主張するか、または、自己の占有に前の占有者の占有をあわせて主張するかを自由に選択することができる(187条1項)*。
* たとえば、前の占有者の占有期間が13年、占有承継人の占有期間が8年であったとすると、占有承継人はあわせて21年間の占有継続を主張することができる。
前の占有者の占有をあわせて主張する場合には、その瑕疵*をも承継する(同条2項)。つまり、前の占有者の占有に瑕疵がある場合には、その占有を承継した者の占有に瑕疵がなかったとしても、あわせて主張する占有は全体で瑕疵があるものとなる。
* 悪意や有過失、強暴、隠匿、他主といった占有の態様のこと。
逆に、前の占有者の占有に瑕疵がない場合には、あわせて主張する占有も全体で瑕疵がないものとなる。
したがって、前の占有者がその占有開始の時点で善意無過失であった場合には、たとえ占有承継人が占有開始時に悪意または有過失であったとしても、あわせて主張する占有について10年の取得時効が成立する(最判昭53.3.6)。

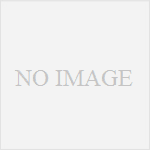
コメント