相続における無権代理の処理
相続開始により、相続人は被相続人の一切の地位を承継する(896条)。
本人と無権代理人が相続人と被相続人の関係にある場合、相続開始によって、①無権代理人が本人の地位を承継し、あるいは反対に、②本人が無権代理人の地位を承継する。また、③第三者が本人の相続人と無権代理人の相続人とを兼ねる場合には、その者が本人の地位と無権代理人の地位をともに承継することが起こりうる。
このように、相続によって本人の地位と無権代理人の地位とが同一人物に帰属した場合に、無権代理をめぐる法律関係をどのように処理すべきかが問題となる。それが無権代理と相続と呼ばれる問題である。
無権代理人の本人相続
1 無権代理人が本人を単独相続する場合
無権代理人が本人の地位(資格)を相続する場合、単独相続か共同相続かで議論の様相が若干異なる。まず、単独相続の場合から検討する。
【設例①】Aが所有する土地をその子Bが無権代理によってCに売却した。その後、Aは死亡し、BがAを単独で相続した。この場合にCはBに対して、購入した土地の引渡しを請求することができるか。
(1) 資格融合説と資格併存説
設例①のような無権代理人が本人を単独相続した場合の法律関係をめぐって、次のような見解が主張されている。
① 資格融合説
相続によって無権代理人の資格と本人の資格とが一体となり、それによって無権代理行為の瑕疵が追完される(欠けている要件が備わって有効となる)と説く見解である。
この見解によると、相続により無権代理行為が追完されることによって、以後、その行為は有効なものとして扱われ、民法117条の無権代理人の責任や本人の追認拒絶権も消滅することになる。したがって、設例の相手方Cは、無権代理につき善意か否か、過失があるか否かを問わず、無権代理人Bに対して土地の引渡しを請求することができる。
この見解は、後述する本人の無権代理人相続の場合において妥当な結論を導くことができないために、学説において支持されていない。
② 資格併存説
相続後も無権代理人の資格と本人の資格が相続人(設例ではB)において併存すると説く見解である。この考え方によると、無権代理人が本人を相続することによって、無権代理人は本人が有していた追認拒絶権をも承継する。
しかし、無権代理人に追認拒絶権が認められるとすると、無権代理人は自ら無権代理行為をしておきながらその履行を拒むことができることになって不当ではないか。そこで、資格併存説のなかでも、無権代理人の追認拒絶に関して、これを否定する説(信義則説)と肯定する説(併存貫徹説)との対立が見られる。
信義則説は、無権代理人が自らした無権代理行為を本人の資格において追認拒絶することは信義則上許されないとする説である。この説に立つと、設例の相手方Cが相続人Bに対して代理行為の効果としての履行の請求をしたとき、Bはその履行を拒むことができない。
併存貫徹説は、無権代理人は本人の資格にもとづいて追認拒絶することができるとする説である。無権代理人の追認拒絶によって相手方は代理行為の効果としての履行請求ができなくなり、また、相手方が無権代理につき悪意または有過失であったときは民法117条の無権代理人の責任を追及することもできない。
この説では、相手方Cに悪意または過失があったときには、Bに対して土地の引渡しを請求することができないことになる。このように解しても、相手方に過失があって表見代理を主張できないような場合には、もとより相手方は本人に対して履行請求できる立場になかったのであるからとくに相手方を不利益にするものではなく、むしろ相続という偶然の事情によって相手方を有利にする理由はないと考える。
(2) 判例の立場
判例は、無権代理人が本人を単独相続した場合において、「本人が自ら法律行為をしたのと同様の法律上の地位を生じ」ると判示する(最判昭40.6.18―無権代理人が他の相続人の相続放棄により単独で本人を相続した事案)。
これは、一見、資格融合説の立場を採用したかのようであるが、単に無権代理行為が当然有効となるという結論を述べたにすぎないようにも解することができる。したがって、資格併存説(信義則説)を採用していると解することも不可能ではない。
後述するように、別の判例は、傍論ではあるが、無権代理人が本人の資格において追認拒絶することは信義則に反するから、無権代理行為は当然有効となると述べている(後掲最判昭37.4.20)。
〔考察〕無権代理人の法定代理人就任
たとえば、AがBを無権代理した後に本人Bの成年後見人(法定代理人)に就任したケースを考える。Aは、Bのために自らがした無権代理行為の追認を拒絶することはできるか。無権代理人が本人を相続する場合に類似しており、判例にも信義則上、追認拒絶することができないとしたものがある(最判昭47.2.18)。しかし、このケースでは本人のために追認拒絶をしており、無権代理人自身のために追認拒絶する相続のケースと同列に論じることはできない。法定代理人に就任した無権代理人Aの追認拒絶が信義則に反するかどうかの判断は、本人の利益の保護という観点から慎重になされるべきであろう。判例も、このような考え方に立つ(最判平6.9.13―無権代理人自身ではなく、無権代理行為に関与した者が本人の後見人に就職した事案)。
2 無権代理人が本人を共同相続する場合
無権代理人のほかに本人の共同相続人がいる場合は、単独相続の場合と異なり、他の共同相続人との利害関係をも考慮しなければならないのでより複雑である。
【設例②】設例①のケースで、Bの単独相続ではなく、BとDの共同相続であったとした場合において、Bは追認を拒絶することができるか。とくにDに追認の意思があるときはどうか。
(1) 追認は可分か不可分か
前提として、本人を共同相続することによって追認権(追認拒絶権)は共同相続人に可分的に帰属するのか、それとも不可分的に帰属するのかという問題がある。
可分的に帰属すると解するのであれば、他の共同相続人が追認を拒絶しても、追認した共同相続人の相続分の限度で無権代理行為を有効とすることができる。
これに対して、不可分的に帰属すると解するならば、一人でも追認を拒絶する共同相続人がいるときには、他の共同相続人すべてが追認を承認しても追認の効力が生じず、無権代理行為は全体として無効となる。
追認の可分性を肯定する場合、設例②において無権代理人Bの追認があるとみなされて、かつ共同相続人Dが追認を拒絶したときには、土地はCとDの共有になる。が、この結果が妥当であるかは疑問である。
共同相続人であるDは、共有者として土地を取得したのであるから、そもそも共有持分の譲渡が自由であることを考えると、他の共有者の変更(B→C)によって見知らぬ者との共有関係を強いられることになってもそれに甘んじなければならないと言える。しかし、Cのほうからすれば、もともと土地を単独所有することを前提に取引の相手方となったのであるから、Dとの共有はCにとって思わぬ不利益となる。
追認の可分性を肯定し、無権代理行為を部分的に当然有効とすることには、このような難点が存在する。
(2) 資格融合説と資格併存説
単独相続の場合と同様に、共同相続の場合においても、資格融合説と資格併存説(信義則説、併存貫徹説)の対立を考えることができる。
① 追認可分の立場
追認可分の立場をとると、融合説では、無権代理人Bは追認を拒絶することが認められず、他の相続人Dが追認拒絶したときには、無権代理行為は無権代理人Bの相続分の限度で当然有効となるが、部分的有効を認めることには上述のような問題が存在する。
信義則説でも、無権代理行為を(相手方Cの効果選択によるのではなく)当然有効と解するのであるならば、同様の結論になる。
② 追認不可分の立場
追認不可分の立場をとる場合、信義則説、併存貫徹説いずれの説をとっても、共同相続人のうち一人でも追認を拒絶する者がいるときには追認の効力は認められない。設例のDが追認を拒絶するかぎり、Bが追認を拒絶できるか否かにかかわらず、無権代理行為は有効にはならない。
ただし、他の共同相続人全員が追認を承認しているのに無権代理人だけが追認を拒絶しようとしている場合は別である。
信義則説に立つならば、無権代理人Bには追認を拒絶する権利がないのであるから、この場合にはBD全員による追認があるとみなすことができる(後掲最判平5.1.21参照)。
これに対して、併存貫徹説に立つのであれば、無権代理人Bにも追認を拒絶する権利があるので、たとえDが追認を承認していたとしても、追認は効力を生じない。もっとも、この結論に対しては不当であるとの批判がある。
無権代理行為が追認により有効とならないときは、相手方は、民法117条の無権代理人の責任を追及することになる(相手方の善意無過失が要件)。
(3) 判例の立場
判例は、「無権代理行為を追認する権利は、その性質上相続人全員に不可分的に帰属」し、「共同相続人全員が共同してこれを行使しない限り、無権代理行為が有効となるものではない」から、「他の共同相続人全員が無権代理行為の追認をしている場合に無権代理人が追認を拒絶することは信義則上許されないとしても、他の共同相続人全員の追認がない限り、無権代理行為は、無権代理人の相続分に相当する部分においても、当然に有効となるものではない」と判示する(最判平5.1.21)。
これを設例②にあてはめると、共同相続人Dが追認しないかぎり無権代理行為は有効とならないが、Dが追認している場合には、無権代理人Bは追認を拒絶することができず、無権代理行為は有効とみなされることになる。
〔参考〕最判平5.1.21(民集)
ある金銭債権についてYがその父Aの無権代理人としてAを保証人とする連帯保証契約を締結した後に、A死亡により、YがAの妻とともにAの権利義務を共同相続したところ、金銭債権の譲受人であるXがYに対して、その相続分に相当する範囲での保証債務の履行を請求したという事案。裁判所は、追認の不可分性を理由に、Yの相続分に相当する部分においても無権代理行為である連帯保証契約が有効になったものということはできないと判示した。
同じ日付で同様の判示を行った最高裁判決がある(判タ)。本人A所有の不動産をその子XがAの無権代理人としてYに売却した後、A死亡によりXらがその不動産を共同相続した事案。XのYに対する抹消登記手続請求を認めた。
3 本人が生前に追認拒絶した場合
【設例③】Aの子Bが無権代理によってA所有の不動産をCに対して処分したが、Aがその追認を拒絶した。その後、Aが死亡してBがAを単独相続した。Bは、Cに対して追認拒絶の効果を主張することができるか。
本人が追認を拒絶すれば無権代理行為は有効でない(本人に効果が帰属しない)ことが確定し、以後は本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができなくなる。そのことは、本人の追認拒絶の後に無権代理人が本人を相続することによって影響を受けるものではないと考えることができる。
そのように考えると、無権代理人が本人が生前にした追認拒絶の効果を主張しても、信義則に反するとは言えない。したがって、無権代理人Bは、本人Aの追認拒絶の効果を主張して相手方Cからの本来の履行請求を拒むことができる。
判例も、同様の理由から、「本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではない」とする(最判平10.7.17)。
学説には、無権代理行為をした当の本人が追認拒絶の効果を享受することは不当であるとして、判例の結論に否定的な意見もある。
本人の無権代理人相続
1 本人の追認拒絶権の行使
【設例④】A所有の土地をその親であるBが勝手にAの代理人としてCに譲渡する契約を締結したが、その後、B死亡によりAがBを相続した。この場合において、CはAに対してどのような請求をすることができるか。
本人が無権代理人を相続した場合、無権代理行為は当然に有効となるものではなく、本人は被相続人のした無権代理行為の追認を拒絶することができる。相続人である本人はもとから追認拒絶権を有しており、無権代理人を相続した後に本人の資格で追認拒絶権を行使したとしても、なんら信義則に反しないからである。
判例(最判昭37.4.20)、学説ともにこの結論を支持する。(資格融合説は、この結論を導けないために支持されていない。)
したがって、相手方Cは、相続人(本人)Aが被相続人(無権代理人)Bのした無権代理行為を追認しないかぎり、Aに対して本来の履行を請求することができない。
2 無権代理人の責任の承継
相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(896条)。無権代理人の相続人は、民法117条による無権代理人の債務(責任)をも承継するのであって、そのことは本人が無権代理人の相続人となる場合においても変わらない。
(1) 本人に対する責任追及の可否
それでは、設例④で、本人Aが無権代理人Bの責任を相続すると考えると、無権代理について善意無過失の相手方CはAに対して無権代理人の責任(損害賠償責任または履行責任)を追及することができることになりそうでうある。
判例も、「本人として無権代理行為の追認を拒絶できる地位にあったからといって右債務〔無権代理人の責任〕を免れることはできないと解すべきである。まして、無権代理人を相続した共同相続人のうちの1人が本人であるからといって、本人以外の相続人が無権代理人の債務を相続しないとか債務を免れうると解すべき理由はない」と判示する(最判昭48.7.3)。
(2) 本人が負う責任の内容
相手方Cが損害賠償責任を選択して追及してきたのであれば、本人Aが責任を負うという結論にとくに問題はない。しかし、相手方Cが履行責任を選択して追及してきた場合が問題である。相続前には本人は追認を拒絶して相手方の(本来の)履行請求を拒むことができたのに、相続という偶然の事情によって相手方の(117条の)履行請求を拒むことができなくなるのは不合理であると考えられるからである。
そこで、無権代理人を相続した本人は、無権代理人の責任を負うとしつつも、原則として相手方からの履行責任の追及を拒むことができるとする見解が有力である。この見解によると、CはAに対して損害賠償請求はできても、土地の引渡請求をすることはできない。
(3) 参考判例―他人物売買のケース
不動産の権利者Aでない者Bが自己の名義で(Aの代理人としてではなく)その不動産を売却した後に、Bが死亡してAらがBを相続したという事案で、権利者Aは相続後も権利の移転につき諾否の自由を有し、信義則に反するような特別の事情のないかぎり、売主としての履行義務を拒否することができるとした判例がある(最大判昭49.9.4)。
A(本人・権利者)からすると、Bが代理人としてであれ、他人物の売主としてであれ、自分の不動産を無断で売却されたことに変わりがないのであるから、無権代理か他人物売買かで結論が異なるのは適当でない。他人物売買の事案についての判例の結論を支持するのであれば、無権代理の事案についてもそれと同様の解釈をするべきであろう。
第三者による無権代理人と本人の相続
第三者が無権代理人と本人の両方を相続する場合として、いろいろなケースが考えられる。判例上問題となったのは、次の設例のように、無権代理人を本人とともに相続した者がその後さらに本人を相続したというケースである。
【設例⑤】A所有の土地をその妻BがAの無権代理人として売却した。その後、無権代理人Bが死亡して本人Aと子のCが相続し、さらに、Aも死亡してCが相続した。この場合において、Cは本件売買の追認を拒絶することができるか。
判例は、このように「無権代理人を本人とともに相続した者がその後更に本人を相続した場合」を、無権代理人が本人を相続した場合と同様に考えて、この場合においては、「当該相続人は本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶する余地はなく、本人が自ら法律行為をしたと同様の法律上の地位ないし効果を生ずる」と解している(最判昭63.3.1)。
無権代理人を相続した者は、自らが無権代理行為をしたわけではない。それにもかかわらず、判例が無権代理人を相続した者を無権代理人と同視するのは、「無権代理人を相続した者は、無権代理人の法律上の地位を包括的に承継する」という理由にもとづく。
これに対して学説は、資格併存説の立場からCの追認拒絶は許されると解している。無権代理人の相続人は無権代理行為を行った当人であるという事情まで承継するものではないから、Cの追認拒絶は信義則に反するものではないと解することができる。

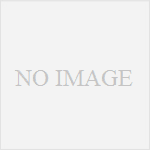
コメント