無効とは
無効とは、当事者が法律行為によって意図した法律効果が初めから発生しないことをいう*。
* 無権代理や他人物売買の場合に効果の帰属先が不確定の状態になることを講学上「無効」と表現することがあるが、これは法律行為の瑕疵を原因とするものではないので、ここにいう無効ではない(不確定無効とよばれる)。
法律行為の無効は、①いつでも、②誰からでも、③誰に対しても、主張することができる。
これが無効の基本的な内容であって、公序良俗違反による無効(90条)や強行規定違反による無効(90条・91条)はこのような内容の無効である。
しかし、無効の内容は、すべての場合について同じではなく、無効原因によって異なることに注意を要する。
相対的無効
無効は、誰に対しても主張することができる。つまり、法律行為の当事者に対してだけではなく、第三者に対しても無効を主張することができるのが原則である(絶対的無効)。
しかし、明文の規定あるいは条文の解釈によって、特定人に対しては無効を主張できないとされる場合がある(93条2項・94条2項など)。このような無効を相対的無効という。
取消的無効
無効は誰からでも主張することができるのが原則であるが、無効が特定人を保護することを目的とする場合には、その者以外からの主張を認める必要はない。
意思無能力を理由とする無効(3条の2)は、表意者保護の観点から、表意者以外の者が主張することはできないと解されている。
特定人のみが主張できるという点が取消権者のみが主張することができる取消しと似ているので、このような無効を取消的無効という。
一部無効の問題
法律行為の内容の一部に関して無効原因がある場合、その部分のみが無効(一部無効)となるのか、それとも法律行為全体が無効(全体無効)となるのかという問題がある。一部無効の問題と呼ばれる。
明文の規定が存在するときは、それによる*。たとえば、利息制限法1条1項は、金銭消費貸借契約における利息に関して一定利率を超える場合にその超過部分だけを無効としている⁑。
* 民法上、無効の範囲を定めた規定として、278条1項、360条1項、410条、580条1項、604条1項などがある。
⁑ 著しく高利の利息を定めた場合には暴利行為(公序良俗違反)とされ、契約全体が無効となることもある。
明文の規定が存在しないときは、無効な部分を取り除いたうえで(欠缺が生じたときは補充して)法律行為の効力を維持すべきかどうかの判断を、さまざまな観点から検討して行う*⁑。
* ①無効原因が存在する部分とその他の部分を分離することが可能か、②一部無効としても規制の目的を達成しうるかどうか、③効力を維持することが当事者の意思に反しないか、など。一般に、私的自治への介入は必要最小限度にとどめるべきであるから、できるだけ法律行為の効力を維持すべきであると考えられている。
⁑ 芸娼妓契約に関する最判昭30.10.7は、契約内容の一部(稼働契約)に関して無効原因(公序良俗違反)が存在する場合に、当該部分は他の部分(金銭消費貸借契約)と密接に関連して互いに不可分の関係にあるとして契約全体を無効とした。
無効行為の追認
無効な法律行為は、追認によって遡及的に有効とすることができない(119条本文)。
当事者が無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなされる(同条ただし書)。新たな行為は当事者が追認した時から効力を生じる*。
* 意思無能力を理由とする無効は、表意者からの遡及的追認が認められるべきであると解されている。無効が表意者保護を目的とする以上、その表意者の追認によって無効行為を当初から有効として扱っても不都合はないからである。
新たな法律行為は、追認の時点でその行為の成立要件・有効要件を満たしていなければならない*。
* 公序良俗違反または強行規定違反による無効は、違反の状況が改善しないかぎり、追認をしても有効とはならない。
無効行為の転換
無効行為の転換とは、無効な法律行為が他の種類の法律行為としての要件を備えている場合に後者の法律行為として有効に扱うことをいう。
約束手形の振出しが無効である場合にそれを準消費貸借契約(588条)として有効に扱うことや、無効な地上権設定契約を賃貸借契約として有効に扱うことなどが、無効行為の転換の例である。
無効行為の転換は、私的自治に介入して、当事者が当初意図した効果とは別の効果を与えるものであるから、その認否を慎重に決めなければならない。無効行為と他の法律行為とが事実上同じ目的を達成できるものであって、当事者がもし無効を知っていたなら他の法律行為としての効果を意欲したであろう場合にかぎり認められるべきである。
要式行為への転換
無効な要式行為から他の要式行為への転換も、その方式を要求した法の趣旨に反しないかぎりにおいて認められる余地がある。
秘密証書遺言から自筆証書遺言への転換(971条)のように、意思表示を慎重・明確にするために方式が要求されている場合には転換が認められやすい。しかし、手形行為のように法が一定の方式以外を認めない趣旨である場合には、転換は認められない。
要式行為への転換がとくに問題となるのは、認知、養子縁組といった身分行為の転換についてである*。
* 判例は、嫡出でない子についてその父がした嫡出子出生届に認知としての効力を認める(最判昭53.2.24)。しかし、他人の子を自分の子として出生届や認知届をしても、養子縁組としての効力を認めない(最判昭49.12.23、最判昭54.11.2)。

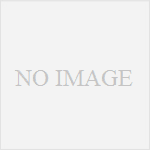
コメント