消滅時効の対象となる権利
消滅時効は、権利を行使しない状態が一定期間継続した場合にその権利の消滅を認める制度である。
消滅時効の対象となる権利は、①債権(166条1項)と、②債権または所有権以外の財産権(同条2項)である。後者の例として、用益物権(地上権・永小作権・地役権)がある。
消滅時効にかからない権利
所有権は、消滅時効にかからない*。その帰結として、所有権に基づく物権的請求権や登記請求権、共有物分割請求権(256条)、相隣権(209条以下)といった所有権から派生する権利も消滅時効にかからないと解されている。
* 他人が所有権を時効取得すると元の所有者の所有権が消滅するが、これは取得時効の反射的効果にすぎない。
担保物権(先取特権・質権・抵当権)は、原則として被担保債権とは独立に消滅時効にかかることはないが、被担保債権の時効消滅によって当然に消滅する(付従性)。
形成権が消滅時効にかかるかどうかについては議論があるが、判例は形成権の消滅時効を肯定し、債権に準じて扱うとしている(最判昭62.10.8など)。
消滅時効期間の起算点
消滅時効の進行がいつ開始するか(起算点)は、権利の種類や時効期間に応じて異なる。
債権の消滅時効の起算点は、①5年の消滅時効の場合は「債権者が権利を行使することができることを知った時」(主観的起算点)、②10年の消滅時効の場合は「権利を行使することができる時」(客観的起算点)である(166条1項)。
債権・所有権以外の財産権の消滅時効の起算点は、「権利を行使することができる時」である(同条2項)。
「権利を行使することができる」の意味
「権利を行使することができる」とは、権利の行使につき法律上の障害がないことを意味する*。
* 判例はさらに、権利の性質上、権利行使が現実に期待のできるものであることをも必要としている(最大判昭45.7.15)。
この要件は、5年の消滅時効の場合にも要求される。客観的に権利行使が可能である状態でなければ、権利の不行使があったとはいえないからである。
たとえば、期限(始期)や停止条件は法律上の障害であるので、期限到来・条件成就するまでは消滅時効の進行は開始しない*。
* 不確定期限付き債権・停止条件付き債権の場合、客観的起算点は期限到来・条件成就の時、主観的起算点は債権者が期限到来または条件成就の後でそれらの事実を知った時である。
⁑ 確定期限付き債権の場合、期限到来の時期が明確であるので、期限が到来する前に「債権者が権利を行使することができることを知った」といえる状態にある。したがって、期限が到来した時点から5年の消滅時効が進行する。
一方、期限の定めのない債権は、いつでも債務者に履行を請求することができるのであるから、原則として債権発生の時点が「権利を行使することができる時」となる*。
* 契約に基づいて発生する債権だけでなく、不当利得返還請求権などの法律の規定に基づいて発生する債権についても同じである。
なお、同時履行の抗弁権の存在(533条)は、時効の進行を妨げない。債権者は自己の債務の履行を提供することによって相手方に履行を請求することができるからである。
以上に対して、権利者の病気・不在、権利の存在を知らないことなどは、法律上の障害ではなく事実上の障害であるので、時効の進行を妨げない。
消滅時効期間
消滅時効完成に必要な期間(消滅時効期間)の長さは、権利の種類や起算点に応じて異なる。
債権の消滅時効期間は、①債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年、②権利を行使することができる時(客観的起算点)から10年である(166条1項)。
①と②のどちらかが先に経過した時に消滅時効が完成する。
債権または所有権以外の財産権の消滅時効期間は、20年である(166条2項)。
消滅時効期間の例外
一定の種類の権利については、166条の一般原則とは異なる消滅時効期間が法定されている。
たとえば、不法行為による損害賠償債権の消滅時効期間は、①被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年、②不法行為の時から20年になる(724条)*。
* そのほかの例外として、定期金債権に関する168条や、判決で確定した権利に関する169条などがある。
人の生命または身体の侵害による損害賠償債権は、債務不履行に基づく場合には権利を行使することができる時(客観的起算点)からの時効期間が20年となり(167条)、不法行為に基づく場合には損害および加害者を知った時(主観的起算点)からの時効期間が5年となる(724条の2)。
結論として、債務不履行と不法行為のいずれの構成をとっても、消滅時効期間は同じになる(主観的起算点から5年、客観的起算点から20年)。
これは、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求については、財産的利益の侵害による場合よりも権利行使の機会を長く確保する必要性が大きいので、その消滅時効期間を長期化する趣旨である。
消滅時効に類似する制度(除斥期間)
消滅時効に類似した制度として除斥期間がある。
除斥期間とは、権利関係を速やかに確定させることを目的として法が定めた権利の存続期間をいう。
除斥期間は、時間の経過により権利が消滅するという点で消滅時効と類似する。しかし、次のような点で消滅時効とは異なる。
- 更新がない。
- 援用が不要である(法律上当然に消滅する)。
- 権利発生時を起算点とする。
- 効果が遡及しない。
期間制限の性質
条文上、個々の権利ごとに定められている行使期間の制限が、消滅時効期間と除斥期間のいずれであるかが問題となることがある。
一般的に、請求権について1年などの短期の期間の定めがある場合は、権利関係の早期確定を図る趣旨であるから、その期間の性質は除斥期間であると解されている。
また、形成権について期間の定めがある場合、更新を考える余地がないので、その期間の性質は除斥期間であると解される(通説)*。
* 判例は、126条(取消権)の期間について法文どおりに消滅時効期間とする一方で、566条3項(解除権)の期間については除斥期間とする(最判平4.10.20)。
- 形成権について期間の定めがある場合
- 126条(取消権―5年・20年)
- 566条3項・637条1項(解除権―1年)
- 請求権について短期の期間の定めがある場合
- 193条(盗品・遺失物の回復請求権―2年)
- 195条(動物の回復請求権―1か月)
- 201条1項・3項(占有保持・回収の訴え―1年)
- 566条3項・570条・637条1項(履行追完・報酬減額・損害賠償請求権―1年)
- 600条・621条(損害賠償・費用償還請求権―1年)
- 長短二重の期間の定めがある場合
- 126条(取消権―5年・20年)
- 168条1項(定期金債権―10年・20年、ともに消滅時効期間)
- 426条(詐害行為取消権―2年・10年、ともに出訴期間)
- 724条(損害賠償請求権―3年・20年、ともに消滅時効期間)
- 884条(相続回復請求権―5年・20年)
- 1048条(遺留分減殺請求権―1年・10年)
- 製造物責任法5条1項(損害賠償請求権―3年・10年)
- 消費者契約法7条1項(取消権―6か月・5年)
消滅時効や除斥期間に類似するものとして、権利失効の原則がある。
権利失効の原則とは、権利者が永く権利を行使しないことによって相手方にもはや権利が行使されないだろうという信頼を生じさせた場合、その信頼を裏切って権利を行使することは信義則に反して許されない、という考え方をいう。
この原則を認めると、消滅時効期間や除斥期間が経過する前、あるいは、消滅時効にかからない権利(物権的請求権など)であっても、権利の行使を阻止することができるようになる。
判例は、一般論としてこの原則を認めているが(最判昭30.11.22)、実際にこの原則の適用により権利行使を阻止した例はまだない。

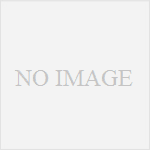
コメント